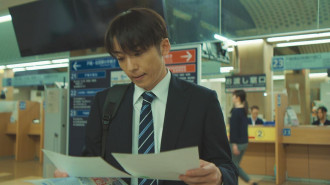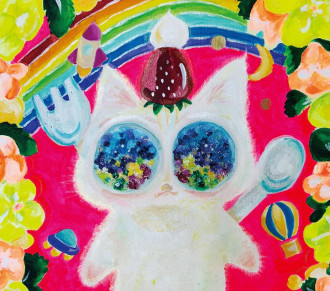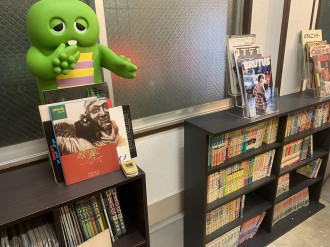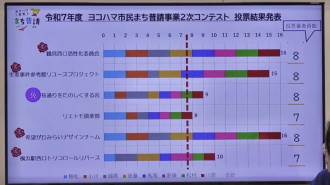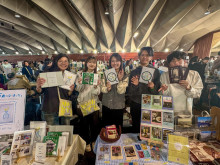創造都市を学ぶ「創造都市スクール2025」が開講
全12回/無料・会場+配信・交流&アーカイブ視聴

横浜市の「創造都市」の歴史—2004年の提言から20年以上の蓄積
「文化芸術創造都市」提言と創造界隈の形成
2004年1月14日の有識者提言「文化芸術創造都市―クリエイティブシティ・ヨコハマ」は、都心臨海部の停滞に対し、文化芸術の創造力を都市再生の主軸に据える方針を示した。柱として、臨海部を中心とした暫定利用の推進、クリエイター集積と創造産業の育成、市民参加を伴うネットワーク形成、「創造界隈」の形成などが掲げられた。
市は2004年4月に「文化芸術都市創造事業本部」を設置。2006年4月の局再編で「開港150周年・創造都市事業本部」へ改組し、推進体制を強化。クリエイター集積と歴史建築の活用、公共空間での実験、イベントや国際展の展開を連鎖させた――こうした取り組みが、関内・関外~みなとみらいを核とする創造界隈の可視化と拠点化へつながり、現在に続く政策フレームにも反映されている。
創造都市はソフトとハードを一体で進める考え方
創造都市は、横浜市が2004年に文化芸術創造都市構想を発表して以来、公民連携で都市デザイン・文化振興・産業振興の交差点で展開されてきた政策の一環である。横浜市は「創造都市(クリエイティブ・シティ)」を、文化と経済の両面で活力を失いつつあった都心臨海部の再生に向け、文化芸術の創造性を生かし、ソフト(文化・経済振興)とハード(まちづくり)を一体で進める考え方として位置づけ、「市民にとって誇れるまち」「国内外から選ばれる都市」をめざすと説明している。
施策は具体の取組群としても示され、創造界隈拠点、創造界隈形成推進委員会、アーツコミッション・ヨコハマ(ACY)、芸術不動産、映像文化都市、横濱ジャズプロムナード、創造的産業の振興などが並ぶ。実施母体・連携スキームへの言及を伴う「創造都市の取組」ページで体系的に公開されている。
創造都市の取組(横浜市)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/bunka/sozotoshi/sozotoshi/
スクールのねらい—横浜の知見を束ね、次世代の担い手を育成
現場知を体系化する学びの場
創造都市スクール2025は、横浜市立大学に加えて、横浜国立大学、神奈川大学、BankART1929、横浜コミュニティデザイン・ラボ、横浜都市みらいが実行委員会を構成する。講義はオンライン併用で行い、全国の自治体職員・NPO職員・アートプロジェクト関係者等広く参加を期待している。
横浜の20年で蓄積した政策・拠点運営・プロジェクトの実践知を、講義/対話/公開収録とライブ配信で再編集し、理論と現場を往復する創造都市スクールは、文化庁の補助事業として2024年度に開講。創造界隈形成、歴史建築の暫定活用、芸術不動産、公共空間での社会実験、文化イベント運営、クリエイティブ産業振興といった論点を横断し、国内外事例との比較、意思決定プロセスなどさまざまな切り口で創造都市の取り組みを紹介してきた。
越境学習で実務に直結
行政・企業・NPO・研究者・学生が肩書を越えて学び合い、セッション内の質疑と終了後の交流会を通じて、地域横断のネットワークと小規模な協働の芽を生む。創造・クリエイティブと都市に関心がある人たちのネットワーク形成を促し、受講者それぞれの現場での活用に結び直す。受講生登録をするとライブ配信の受講の他、アーカイブでいつでも視聴できる運営設計とした。テーマ横断型で、学び直しと知見の共有を後押しする狙いで展開してきた。
開催概要—全12回・毎週木曜19:00、ExPLOT Studio+オンライン
 会期・時間・方式
会期・時間・方式
創造都市スクール2025の会期は、9月18日(木)~12月4日(木)で全12回の講座を実施する。原則毎週木曜19:00~20:30で実施(※9/24のみ水曜)。受講は無料・事前登録制で、会場参加とオンライン同時配信を併用するハイブリッド方式で実施する。
会場・定員・案内
会場はExPLOT Studio(横浜市西区みなとみらい4-3-1 PLOT48 テラス棟1F)、定員50名。申込者には参加方法や配信URL等を順次案内する。
開催概要—全12回・毎週木曜19:00、ExPLOT Studio+オンライン

【全12回プログラム】
◆第1回(9/18・木)[オンライン開講]
「創造都市の世界的潮流」/講師:佐々木雅幸(大阪市立大学 名誉教授)/ナビゲーター:鈴木伸治
◆第2回(9/24・水)[公開収録]
「創造都市横浜のはじまりと都市デザイン」/講師:野原卓/ナビゲーター:上野正也・小泉瑛一
◆第3回(10/2・木)[公開収録]
「創造都市横浜のDNAをフカボル」/講師:鈴木伸治
◆第4回(10/9・木)
「まちづくりをイノベートする」/講師:嶋田悠介/コメンテーター:野原卓
◆第5回(10/16・木)[公開収録]
「水辺からみた創造都市」/講師:岩本唯史
◆第6回(10/23・木)
「生活と建築から都市をイノベートする」/講師:連勇太朗/コメンテーター:野原卓
◆第7回(10/30・木)
「Art Center NEWを開いてみたら」/講師:小川希
◆第8回(11/6・木)
「BankParkがめざすもの」/スピーカー調整中/ナビゲーター:鈴木伸治
◆第9回(11/13・木)[公開収録]
「関内外をめぐるアートスペース」/講師:稲吉稔
◆第10回(11/20・木)
「Yurakucho Art Urbanismについて」/講師:長谷川隆三
◆第11回(11/27・木)
「創造都市の未来・クリエイティブな都市とは何か?」/講師:岡部友彦/ナビゲーター:秋元康幸/コメンテーター:鈴木伸治
◆第12回(12/4・木)
「みなとみらい21のクリエイティブコミュニティを創る」/講師:小島健嗣/コメンテーター:古木淳/ナビゲーター:秋元康幸
学びやすさ—無料・ハイブリッド・アーカイブ+交流
「今年度の創造都市スクールは、実行委員会形式のもと、市内の新拠点とも連携しながら、横浜国立大学・神奈川大学と協働でプログラムを設計した。昨年度のアーカイブも活用し、実践と学びを往復できる場を提供する」と横浜市立大学の鈴木伸治教授は語る。対象として想定するのは、地域で創造的な実践に取り組む行政・企業・NPO・学生など幅広い層。
昨年度の成果と記録を土台に、今年度は現場志向のセッションを強化。アーカイブ視聴とライブ講座を組み合わせ、関心のある方がいつでも学び直せる仕組みを用意している。
鈴木教授は、「新たな拠点やネットワークと結び、横浜から次のアクションを生み出します。」 とも話している。
プログラムディレクター

横浜の創造都市の現場に携わる6人がプログラムの設計を統括した。
・鈴木伸治(横浜市立大学)— 創造都市論・都市デザインの視点から全体設計を統括。
・野原卓(横浜国立大学)— 都市デザイン史と政策文脈を接続し、公開収録回を主導。
・上野正也(神奈川大学)— 都市計画・地域マネジメントの実装に橋を架ける。
・小泉瑛一(about your city)— プロジェクト編集とポッドキャストでの情報発信を担う。
・神永侑子(AKINAI GARDEN STUDIO)— 商い×まちの視点で場づくりと関係構築を編成。
・秋元康幸(BankART1929)— 文化拠点運営の知見を反映し、現場志向のセッションを強化。
創造都市は—“プロジェクトが連鎖する運動”

創造都市は、固定化された設計図ではなく、分野横断の協働と小さな実験が連鎖し続ける“運動”として捉えられる。アートや建築、産業、福祉、教育といった領域をまたぎ、市民・NPO・企業・大学・行政が役割を持ち寄る。現場から企画を立ち上げ、試行を重ねていく。その循環が次の企画を呼び、都市に住み暮らす人々の創造性が持続的に発揮されるようになる。
核にあるのは、人と人との関係のマネジメント。意思決定のプロセスを開き、成果も失敗も可視化し、記録と共有で学習を蓄積する。運営を通じて出会いと試行錯誤が循環する設計が要となる。横浜では、歴史的建築の暫定活用や公共空間での社会実験、創造界隈の形成が、こうした考え方を具体化してきた。創造都市スクールは、この“運動”を支える理論と実装の往復を扱い、各受講者が自らの現場で「小さく始めて回す」ための方法と関係資本を獲得する場として位置けられている。
次の10年へ、知と現場をつなぐ起点に
9月18日~12月4日の全12回の受講無料の講座の受講登録者は、各回のアーカイブに加え、2024年度の全44講義も視聴できる。各回後の交流の時間は、行政・企業・NPO・研究者・学生が越境して結び直す場となる。
実行委員会では、今年12月にフォーラムの開催も計画している。20年以上の創造都市・横浜のアクションの蓄積と新拠点の動きが交差するいま、創造都市スクールのプログラムは知とネットワークを現場の実装へ接続する「プラットフォーム」として機能していくのだろう。今後、横浜からどのようなプロジェクトが立ち上がるか、次の10年を見据えて注目したい。
創造都市スクール2025
https://creativecity.yokohama/900/2025/09/08/